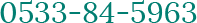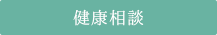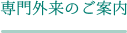- 抜け毛・薄毛
- 起立性調節障害
- コロナ後遺症
- 口腔内灼熱症候群・舌痛症
- 過敏性腸症候群
- 突発性難聴
- 顔面神経麻痺
- 機能性ディスペプシア
- 逆子
- 不妊治療
- うつ病
- 双極性障害
- 鍼灸治療全般
- 小児便秘
- 小児疾患全般
- いぼ痔、切れ痔
- 潰瘍性大腸炎
- 視神経乳頭炎
- 黄斑変性症
- ドライアイ
- 男性不妊、ED治療
- 陣痛促進
- 自律神経失調症
- 頭痛
- 交通事故
症状別Q&A 7ページ目
抗がん剤を使ってから大量に毛が抜けてしまいました
抗癌剤など薬剤の副作用により全身の毛が抜けることはよくあります。
これは、抗がん剤は分裂が活発な細胞に強く影響するからです。そのため、細胞分裂が盛んな毛母細胞(毛をつくるもとになる細胞)は、抗がん剤の影響を受けやすく、毛根がダメージを受けることから脱毛につながるからです。
鍼灸治療の場合、抗がん剤の影響を受けた抜け毛(脱毛)にも対応しています。
これは、抗がん剤は分裂が活発な細胞に強く影響するからです。そのため、細胞分裂が盛んな毛母細胞(毛をつくるもとになる細胞)は、抗がん剤の影響を受けやすく、毛根がダメージを受けることから脱毛につながるからです。
鍼灸治療の場合、抗がん剤の影響を受けた抜け毛(脱毛)にも対応しています。
出産したら抜毛が酷くなりました
妊娠中から出産後にかけてホルモンバランスが乱れることから分娩後の女性に脱毛が起こることがあります。
通常は半年から1年ぐらいで自然に回復しますが、難産であったり、持病をお持ちの場合、育児の負担が多い場合、高齢出産など体力の回復に時間がかかる場合は症状の回復も遅くなり、完治が難しい場合もあります。
こんな時に効果を発揮するのが鍼灸治療です。分娩後脱毛でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
こんな時に効果を発揮するのが鍼灸治療です。分娩後脱毛でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
円形脱毛症にも鍼灸治療は効果がありますか
円形脱毛症は、昔から10円ハゲと呼ばれている円形状の脱毛です。多発して頭全体の毛が抜けることや、全身の毛が抜ける場合もあります。
ストレスが引き金で自律神経や女性ホルモンのバランスが崩れること、自己免疫疾患によるものと考えられています。
鍼灸治療では、自律神経を整えることでストレスの緩和と同時に自己免疫の正常化をはかり、かつ直接患部の脱毛にもアプローチします。
鍼灸治療では、自律神経を整えることでストレスの緩和と同時に自己免疫の正常化をはかり、かつ直接患部の脱毛にもアプローチします。
薄毛や抜け毛になんで鍼灸治療が効くのですか
東洋医学では、髪の毛のことを「血の余り」と呼んでいます。血液に十分な余裕があれば髪の毛まで栄養が行き渡り、髪が健康に育つからです。
食事などで取り込んだ栄養は、生命維持の優先度の高い箇所から行き渡ります。そのため髪の毛など命に影響のない場所は、供給される栄養が手薄になります。その結果、髪の毛の抜け毛や薄毛に繋がります。
鍼灸治療では、以上のような東洋医学的視点を考慮し、かつ現代医学的な観点からも一人ひとりに合わせた最適な治療プランをご提供します。
鍼灸治療では、以上のような東洋医学的視点を考慮し、かつ現代医学的な観点からも一人ひとりに合わせた最適な治療プランをご提供します。
薄毛・抜け毛の鍼灸治療の特徴を教えてください
薄毛・抜毛に対する鍼灸治療の特徴は主に以下の5点となります
・鍼灸治療は根本的な体質改善が可能
・鍼灸治療は発毛スピードを加速化
・鍼灸治療は再生医療
・鍼灸治療は副作用なし
・鍼灸治療は安価で早く効果が出ます
治療費はどのくらいかかりますか
薄毛や抜け毛の治療費は、初回5000円、2回目以降4000円(中野は初回5500円、2回目以降4500円)となります。
薄毛、抜け毛の状態によっては数回治療が必要となりますが、目安は1~2週間に1回の治療となります。
一般的に、薬局やホームセンターで販売している育毛剤は、月1,000~3,000円ですが、薄毛に対して発毛効果はありません。薬局で販売しているミノキシジル配合の育毛剤は月8,000円前後ですが、医療機関での治療と比べると使用量は少なく、患者さん一人ひとりに適切な処置かは判別できません。
薄毛、抜け毛の状態によっては数回治療が必要となりますが、目安は1~2週間に1回の治療となります。
一般的に、薬局やホームセンターで販売している育毛剤は、月1,000~3,000円ですが、薄毛に対して発毛効果はありません。薬局で販売しているミノキシジル配合の育毛剤は月8,000円前後ですが、医療機関での治療と比べると使用量は少なく、患者さん一人ひとりに適切な処置かは判別できません。
一方、デュタステリドやミノキシジルの内服薬では月に約16,000円~30,000円を半年から1年継続します。
その他、HARGなど頭皮に直接注射で、薬剤や再生医療で使用する幹細胞を注入する方法約15万円ほど。
さらに植毛では50万円~80万円、中には300万円かかることもあります。
鍼灸院にはどんな時に行くものですか?
何か体の不調を感じた時、まずは病院に行かれる方がほとんどだと思います。
そして検査で異常がなかったり、湿布や痛み止めの薬で効果を感じなかった時に初めて鍼灸治療を試してみようという選択肢が出ると思います。
鍼灸院に行く方がいい時は痛み、こり、しびれ、不調(例えばめまい、耳鳴り、冷え性、食欲不振、便秘、不眠、生理痛)などがある時です。
その中でも寝違いやギックリ腰、頭痛などは鍼灸治療を早期で始めた方が回復が早い場合が多いため鍼灸院を第一選択に入れることをお勧めします。
ただし、当院でも治療に入る前に問診や検査をして、身体がどんな状態であるかを診断させていただき、症状によっては病院をすすめる場合もあります。
また、潰瘍性大腸炎や不妊治療、突発性難聴、逆子などで薬をもらったり検査をしたりしているといったものは鍼灸治療と病院を併用している方も多く、問題もありません。
そして検査で異常がなかったり、湿布や痛み止めの薬で効果を感じなかった時に初めて鍼灸治療を試してみようという選択肢が出ると思います。
鍼灸院に行く方がいい時は痛み、こり、しびれ、不調(例えばめまい、耳鳴り、冷え性、食欲不振、便秘、不眠、生理痛)などがある時です。
その中でも寝違いやギックリ腰、頭痛などは鍼灸治療を早期で始めた方が回復が早い場合が多いため鍼灸院を第一選択に入れることをお勧めします。
ただし、当院でも治療に入る前に問診や検査をして、身体がどんな状態であるかを診断させていただき、症状によっては病院をすすめる場合もあります。
また、潰瘍性大腸炎や不妊治療、突発性難聴、逆子などで薬をもらったり検査をしたりしているといったものは鍼灸治療と病院を併用している方も多く、問題もありません。
鍼灸治療はどんな症状に効きますか?
鍼灸は「痛み・こり・しびれ・自律神経の乱れ」の治療を得意としています。
代表的なものが肩こり・腰痛です。
慢性的なこりや寝違え、ギックリ腰などの急な痛みにも有効ですが
頭痛や手足のしびれ、抜け毛にも効果があります。
また当院は
・難聴、めまい、顔面神経麻痺などの耳鼻科疾患
・過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、機能性ディスペプシアなどの消化器疾患
・不妊症、逆子、生理痛などの婦人科疾患
・不眠、動悸、起立性調節障害などの自律神経疾患
・夜泣き、夜尿症などの小児疾患
などの専門外来があり、多くの患者さんを治療しています。
代表的なものが肩こり・腰痛です。
慢性的なこりや寝違え、ギックリ腰などの急な痛みにも有効ですが
頭痛や手足のしびれ、抜け毛にも効果があります。
また当院は
・難聴、めまい、顔面神経麻痺などの耳鼻科疾患
・過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎、機能性ディスペプシアなどの消化器疾患
・不妊症、逆子、生理痛などの婦人科疾患
・不眠、動悸、起立性調節障害などの自律神経疾患
・夜泣き、夜尿症などの小児疾患
などの専門外来があり、多くの患者さんを治療しています。
赤ちゃんでも鍼灸治療できますか?
治療に年齢の制限はありません。
だいたい、生後1ヶ月検診を受けてから治療を始めるという場合が多いです。
小さな子どもを治療に連れてくるのは「泣いてしまうかも」とか「うるさくしちゃうから…」と気にされる親御さんもいるかもしれませんが、子どもが泣いてしまうのも成長のひとつです。当院では開院当初から小さな子どもたちへの治療をしているので、安心してお越しください。それでも気になるという親御さんは、電話もしくはLINEでご相談ください。
だいたい、生後1ヶ月検診を受けてから治療を始めるという場合が多いです。
小さな子どもを治療に連れてくるのは「泣いてしまうかも」とか「うるさくしちゃうから…」と気にされる親御さんもいるかもしれませんが、子どもが泣いてしまうのも成長のひとつです。当院では開院当初から小さな子どもたちへの治療をしているので、安心してお越しください。それでも気になるという親御さんは、電話もしくはLINEでご相談ください。
妊娠中でも鍼灸治療はできますか?
治療できます。
つわりや逆子、陣痛促進など様々な症状に治療をおこなっております。
また、切迫流産等の予防に鍼灸治療は効果的なので、妊娠中は積極的に安産目的の鍼灸治療をおすすめします。
つわりや逆子、陣痛促進など様々な症状に治療をおこなっております。
また、切迫流産等の予防に鍼灸治療は効果的なので、妊娠中は積極的に安産目的の鍼灸治療をおすすめします。